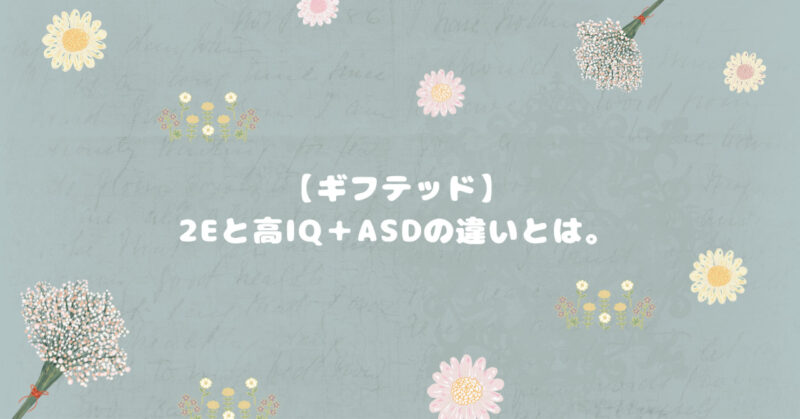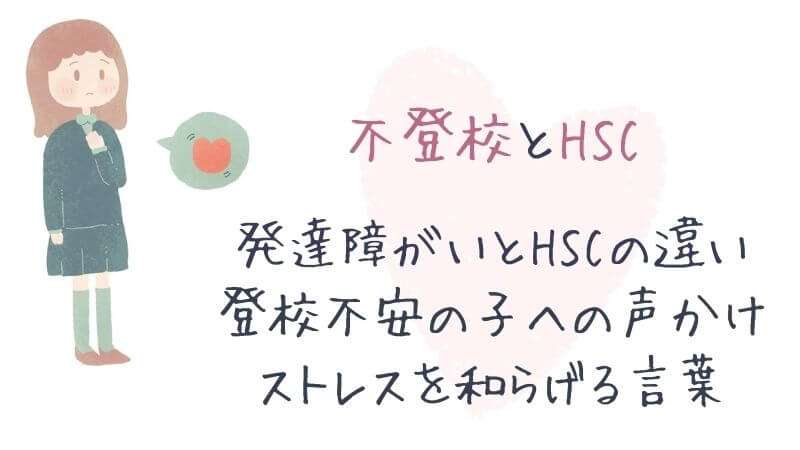ギフテッド(gifted)という言葉は、医学的な診断名ではありません。
そのため、医師から「あなたのお子さんはギフテッドです」と診断を受けることはできません。
当サイトでは、以前の記事
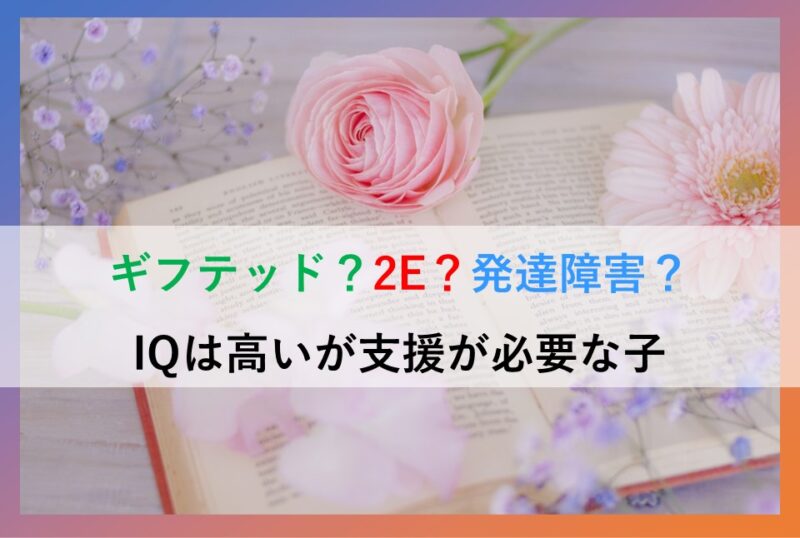
で紹介した定義に基づいて「ギフテッド」や「2E(発達障害と高IQを併せ持つ子)」という言葉を使っています。
高IQの子の生活面・対人面での困りごとを理解しようとしたとき、発達障害の子育て方法の中に参考になるヒントはたくさんあります。
けれど、それだけで全ての問題を解決できるとは限りません。
特に不登校になってしまった場合は、「ギフテッド」という特性を理解せずに環境を整えるのはとても難しいのです。
- 知的好奇心が強いのに、学校に行けない。
- 正義感が強すぎて、理不尽なことに心が折れてしまう。
- 感受性が豊かで、音・光・人の感情にも敏感に反応してしまう。
そんな繊細でエネルギッシュなお子さんを育てている方へ。
この記事では、「2E」と「高IQ+ASD」の違いを、私自身の体験を交えながら、わかりやすく解説していきます。
ギフテッドは高IQのASD?それともまったく別もの?

ギフテッドなんて言っているけど、結局は高IQのASD(自閉スペクトラム症)じゃないの?



発達障害と認めたくない親が“ギフテッド”と言い張っているだけでは?
──そんな声を耳にしたことがある方も多いかもしれません。
確かに、ギフテッドとASDには重なる特性があり、外から見ただけでは区別が難しいこともあります。
けれど、両者には本質的な違いも存在します。
「ギフテッド」と「発達障害」は別の概念
世界的にも知られる書籍
では、ギフテッドが発達障害と誤診されやすい理由や、両者の違いが詳しく紹介されています。
私自身は、カテゴリーにこだわりすぎる必要はないと感じています。
人の脳の構造は一人ひとり異なり、単純に「ASD」「ギフテッド」と分けられるものではありません。
大切なのは、「その子の特性に合った理解と支援をどう進めるか」。
ASD・ギフテッドの両方を学びながら、その子に合う部分を柔軟に取り入れていくだけで十分だと思います。
ASDは「人の気持ちが分からない」だけではない
ASD=人の気持ちが分からない、コミュニケーションが苦手、というイメージがいまだに根強いですが、これはごく一部の特徴に過ぎません。
実際には、
- 感覚が敏感な部分と鈍感な部分がある
- 興味のあることとないことの差が極端
といった「脳の処理の違い」が中心にあります。
つまり、ASDは“欠陥”ではなく“脳のタイプの違いなのです。
「人の気持ちに敏感なASD」もいる
ASDの中にも、「人の気持ちに鈍感なタイプ」もいれば、「人の気持ちに敏感すぎるタイプ」もいます。
むしろ後者は、共感力が強すぎて他人の感情に飲み込まれ、情緒不安定になりやすいこともあります。
娘が通っていた病院の精神科医にもASDの先生がいらっしゃいましたが、とても共感力があり、こちらの気持ちをよく汲み取ってくださいました。
ASD=コミュニケーションができない、というのは大きな誤解です。
このようにASDには、コミュニケーション能力と分析力が必要な職業の方も多いです。
それに人の気持ちに興味がないからと言って、それが直接問題になるわけではありません。
反社会的な行動をとらなければいいのです。
ASDは天才が多い?「パターン・シーカー」という考え方
サイモン・バロン=コーエン著
📘『ザ・パターン・シーカー 自閉症がいかに人類の発明を促したか』(青土社)
では、ASD傾向の人々を「パターン探しの達人(パターン・シーカー)」と呼び、
人類の発明や科学技術を牽引してきた存在として紹介しています。
この本では、人の脳を次のように分類しています。
- S型(システム化脳):仕組みやパターンを理解するのが得意
- E型(共感脳):人との共感や感情理解が得意
- B型:バランス型
エジソン、ビル・ゲイツ、ピアニストのグレン・グールドなどはS型の代表例。
つまり、ASD的な思考が人類の発展を支えてきたとも言えます。
ギフテッドはこの中でも、共感力も備えつつ知識や知的な話題でつながるタイプが多い印象です。
年齢や性別を問わず、「知的好奇心」で共鳴し合える仲間を見つけられた子は、人生がぐっと生きやすくなります。
HSC・APDという新しい視点も
HSC(Highly Sensitive Child:ひといちばい敏感な子)やAPD(聴覚情報処理障害)も、医学的な診断名ではありませんが、学校が苦手なお子さんを理解するうえで大切なキーワードです。
発達障害との違いも、正直分かりません。
ギフテッドもASDも、感覚が敏感すぎる部分があることは確か。
みちはいろいろのそらさんのブログ が分かりやすいです。
城郭情報処理障害(APD)は、子ども達だけでなく私にもあります。
聴力検査ではまったく問題がないのに、聞き洩らしが多いのが悩み。
学校の先生に説明するために、こちらの記事が参考になりました。
💡学校への伝え方の例
「ADHD、ASDだけでも大変なのに、今度はAPD?またか…」と流されがちですが、配慮の仕方を具体的に伝えることが大切です。



名前を呼ぶか肩をたたいて目を合わせてから話してください。
大事な連絡はメモでください。
といった伝え方で、先生も理解しやすくなります。
こちらのアンテナが立っていない時に、聞こえてくる言葉はBGMになってしまうのです。
おすすめ書籍:角谷詩織先生の新刊
『ギフティッドの子どもたち (集英社新書)』(角谷詩織・著)は、ギフテッド支援の第一人者である角谷先生が、初めてご自身の言葉で書かれた一冊。
とてもやさしい視点で、ギフテッドの子どもたちに寄り添う内容になっています。