▶ 第2章:習いごと選びと家庭での工夫
学校に毎日通うのがつらい。
けれど、まったく行かないわけにもいかない。
発達特性やギフテッド傾向をもつ子どもを育てていると、「学校に合わせる」「集団に馴染む」ということが、
想像以上に大きな壁になります。
我が家の息子もその一人でした。
音や人の多さに敏感で、集団の中で過ごすとすぐに疲れてしまうタイプ。
それでも、完全な不登校ではなく、教育支援センターと学校を併用するスタイルで、
小学校を卒業することができました。
この形にたどり着くまでには、
たくさんの試行錯誤と、学校・行政との話し合いがありました。
この記事では、
- どのように支援センターを利用したのか
- 学校との連携で大切にしたこと
- 息子が安定して通えるようになったきっかけ
を、実体験をもとにまとめています。
教育支援センターを活用しながらの登校と、その後の変化
息子は小学4年生のときから、週1〜2日は教育支援センター(旧・適応指導教室)に通い、残りの日を学校で過ごすというスタイルで登校を続けてきました。
「毎日学校に行くことだけが正解ではない」
そう考えるようになったのは、息子の特性を理解し、心の負担を減らすことを最優先にしたかったからです。
※この決断に至るまでの経緯は、別の記事で詳しく紹介しています。
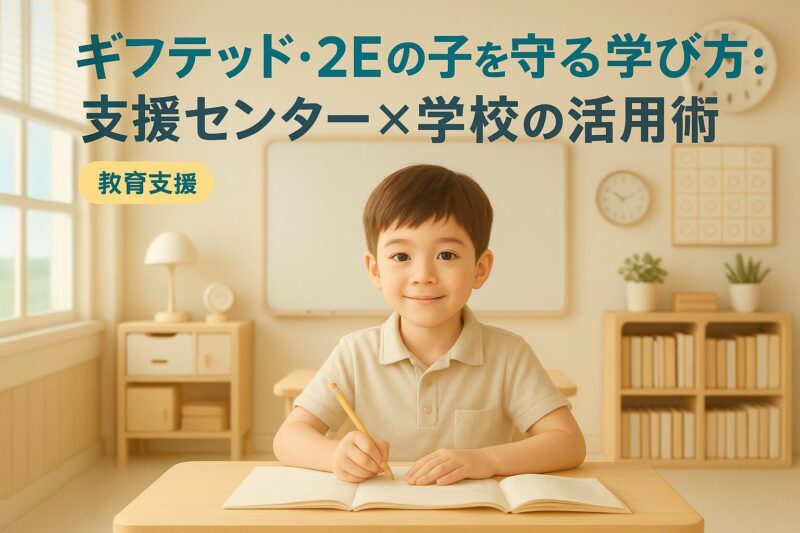
🌿信頼できる先生と出会い、安心できる環境に
5年生のとき、息子はとても相性の良い担任の先生に出会いました。
その先生は、息子のペースを尊重しながら関わってくださる方で、息子も少しずつ心を開き、学校に通うことができるようになりました。
6年生になっても同じ先生に担任をお願いできないか、思い切って学校に相談したところ、
希望を受け入れていただけることになりました。
さらに、息子が信頼を寄せる数少ない友達2人も同じクラスに。
この「安心できる環境」は、息子にとって大きな支えになりました。
 Seiran
Seiran6年生からセンターは週1回にしてみようか?
もし合わなければ、また週2回に戻せばいいよ。
「一度やってみて、合わなければ戻せる」という柔らかい提案が功を奏し、
息子は週1回の通所を選びました。
“一時的に離れる時間”が心を守る
結果的に、最後まで週1回ペースでセンター通いを継続。
それ以外の日は、学校でクラスメイトと一緒に過ごせました。
センターでは、主に塾の宿題をしたり、自習をしたりして静かに過ごしていました。
その時間は、息子にとって「集団から一時的に離れて、心をリセットする日」。
無理に“全日登校”を目指すよりも、
自分のリズムで心を整える時間を持つことが、息子の安定につながったと感じています。
🌱まとめ:子どもが“安心して通える形”を見つけることがいちばん大切
息子が教育支援センターを利用しながら登校を続けられたのは、
「毎日行くこと」よりも「安心して行けること」を優先したからでした。
当初は「学校に通わせなければ」と焦る気持ちもありました。
でも、無理を重ねて心を壊してしまっては意味がありません。
支援センターで過ごす時間は、息子にとって**“心を整える日”**でした。
クラスから少し離れて、自分のペースで過ごすことで、
学校に戻るためのエネルギーを充電できたのだと思います。
学校と行政、そして支援センターの先生方が理解を示してくださったおかげで、
息子は不登校になることなく、小学校6年間を無事に終えることができました。
ギフテッドや2Eの子どもにとって、
「みんなと同じように」よりも、
「自分に合った形で関わり続けること」の方がずっと大切です。
子どもの特性を尊重しながら、少しずつ世界を広げていけるようサポートしていきたい。
それが、私がこの経験から学んだいちばんのことでした。
